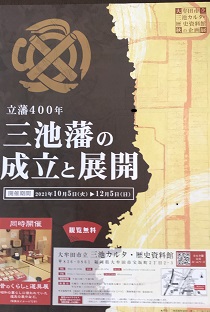三笠神社
高橋紹運公肖像画(神社藏)岩屋城址(太宰府市)江浦城址(みやま市高田町) 内山城址(大牟田市)
三笠神社 境内
由緒
創立年月日 天保六年七月五日
旧社格 県社 (大牟田市及びみやま市高田町の一部)明治九年十月十六日列格
ご祭神 高橋主膳正鎮種(入道号 高橋紹運) 神名 性海霊神
室 齋藤兵部太夫鎭實の妹 神名 花岳霊神
男 立花直次(立花宗茂の弟 三池藩藩祖)神名 玉峰霊神
由緒
高橋紹運公は戦国武将にて、大友氏の一族吉弘氏より出で高橋の名蹟を継がれ筑前岩屋城・宝満城主として主家大友宗麟に忠節を誓い筑前立花城主、戸次道雪と共に大友家を支え守り抜きました。
天正十四年夏、九州制圧をかけ北上する島津軍五万の大軍を迎え討った紹運公の手勢は七百六十三名。「一日で攻め落とす」と豪語する島津氏と十四日間の戦国史上稀に見る激戦となりました(岩屋城の戦い)。紹運公の人柄は『高橋記』に「文武に通じ徳智謀達し、諸人に情深く忠賞も時宜に応じ私欲無く古今稀なる名将と記されています。豊臣秀吉公は「乱世に咲く花」と紹運公を称え長男立花宗茂に柳川藩を次男立花直次に三池藩一万八千石を与えました。直次公は剣術に優れ柳生宗矩の門弟となり「新陰治源流」を開祖。紹運公の妻は二男四女を産み温和な優しい人柄と家中より慕われました。
七代藩主立花種周は、若年寄となり幕政に参与しましたが、文化二年(1805年)奥州伊達郡下手度村(福島県伊達市)移封となり天保六年祖先の義烈を顕彰すべく神祇伯に請いて三笠神社が創建されました。
明治維新により三池復封となり明治三年ご遷座、明治四年縣社に列せられ明治十六年火事により明治二十九年八月現在地にご遷座されました。
以後三笠神社は郷土の発展とともに武勇の神をまつる神社として広く尊崇されています。
立春~春を迎え入れましょう
今年は暖冬の影響で境内の梅が早々に咲き始めました。春の到来を感じます。
気温はまだ低いですが春を告げる梅の花をどうぞご観梅ください。お身体くれぐれもご自愛下さい
謹賀新年

明けましておめでとうございます
旧年中は格別のご厚情を賜り心より御礼申し上げます
皆様のご多幸ご健勝をお祈りしますとともに本年も何卒よろしくお願い申し上げます
令和五年 元旦
新年のご祈祷(ごきとう)のご予約を受け付けております。電話0944-53-0606
厄年の厄除け・家内または社内安全・開運招福・商売繁盛・社運隆昌・合格祈願・良縁祈願・交通安全などさまざまな願意を神様におとりつぎさせていただきます。
喜ばしいことに昨今コロナ感染への恐れが収まりつつあります。
皆様の努力と神さまのご加護によるものと存じます。
神社では、今年も早めに神宮大麻(伊勢神宮)と神社のお札、各種お守り、干支 辰(たつ)の 置物を頒布いたしております。清々しい新年を迎えましょう。
厄年について

秋季大祭 10月27日
午前中は雨模様の中氏子地域を総代様などのご案内でお祓いをしてまわりました。
私どもの来訪を喜んでお迎えいただきいろいろお世話になりました。ありがとうございました。
皆様のご健勝、各家々の幸福を心よりお祈り申し上げます。

秋冷の候 皆様におかれましては益々ご清祥の御事とお慶び申し上げます。
常日頃よりご参拝いただき御礼申し上げます。さて、秋季大祭につきまして、
令和5年10月27日(金)午前8時より祭典開始
午前9時よりお神輿神幸
氏子地域内の家々商店会社などを神社総代さまの案内で神職がお祓いに上がります。
その節は何卒よろしくお願いいたします。
桜花をたたえて~
一雨ごとに暖かくなってまいりました。お彼岸も過ぎ境内の草花が次々に春に向かって咲き始めました。桜花を見ていますと様々な事が思い出されます。咲き初めに心ウキウキ、散り染めに心がしんと静まります。
梅が咲きました 春の訪れです
梅花祭 令和5年2月28日(火)午前10時半ごろから午後3時ごろまで野点(のだて)がおこなわれました。
梅の香匂う境内のあたたかな陽の光の中でおこなわれました。お茶をご参集の方と共に楽しめるありがたさ、神様もご覧になられお喜びになられましたでしょう。裏千家大牟田大牟田支部堺宗美社中の御方々、また、ご参集くださった皆様に感謝申し上げます。
厄年(やくどし)
厄除け(厄よけ)祈願は年末年始にどうぞ
秋季大祭10月27日

秋冷の候益々ご清祥のことと拝察申し上げます。常日頃より御奉賛賜り誠にありがとうございます。さて、お陰様にて氏子崇敬者はじめ衆議院議員・県議会議員先生ご参列のもと無事秋季大祭神事を執り行う事が出来ました。一日も早いコロナ終息と地域発展活性化をみなさまと共に祈りました。ご参集ありがとうございました。
高橋紹運公 肖像画 テレビ放映のお知らせ

テレビ放映のお知らせ
令和4年6月18日(土)
20時~20時55分
BS11「偉人・素顔の履歴書
九州一のキリシタン大名 大友宗麟」 有能な家臣の一人として高橋紹運公が紹介されます。
また、番組はYouTubeでご覧いただけます。
(放送終了後2~3週間視聴可能)
YouTubeで、「偉人素顔の履歴書」と検索すると見逃し配信でヒットします。
令和4年3月12日(土)
20時~20時55分
BS11「偉人・素顔の履歴書 立花宗茂」
父親の高橋紹運公の肖像画が放映されます。
また、番組はYouTubeでご覧いただけます。
(放送終了後2~3週間視聴可能)
YouTubeで、「偉人素顔の履歴書」と検索すると見逃し配信でヒットします。
ぜひご覧くださいませ!!
三池藩について
今年は元和7年(1621年)に三池藩が成立して400年の節目の年です。
柳川藩と三池藩は兄弟ですがそれぞれ別々の独立した藩です。
江戸から明治時代にかけての三池藩の歴史について、春吉省吾著『秋の遠音』(あきのとおね) 上中下三巻に詳しく書かれています。大牟田の歴史の原点につながるとても興味深い本です。
また、大牟田市立三池カルタックス歴史資料館では12月5日まで「三池藩の成立と展開」の企画展が開催されました。こちらの肖像画はかつて中島家所蔵のものでした。
肖像画の修復【令和3年7月27 日】 三池藩立藩400年の節目に

例年7月27日は三池藩主立花家のご参拝がございます。
今年はコロナ感染防止のためご参拝を控えられました。
そこで三池史談会会長大城美知信先生により岩屋城合戦の講話を賜りました。大城先生は『上井覚兼の日記』から合戦に至るまでの状況を読み下され、紹運公の人間味あふれるお姿をご教示くださいました。総代会会員他関係者ありがたく拝聴し紹運公はじめ家臣を偲び御霊を慰めました。
台風、大雨、地震などの自然災害を受け社殿の老朽化が進みゆく中、数年前、初めて御祭神(高橋紹運公)の肖像画の存在を知りました。痛みが激しく専門家によれば「触れれば崩壊しそうな」状態でございました。
そこで、急きょ役員会の議決を受け昨年6月から今年7月にかけて、太宰府市の修理工房 宰匠株式会社に依頼し 九州国立博物館 文化財保存修復施設において修復いたしました。
コロナ感染の影響でお披露目の日程は未定ですが、状況をみてお知らせ致したいと存じます。

端午の節句(5月5日)
例祭日
10月27日
新着情報
岩屋城祉跡参拝へ
総代さんと共に令和2年9月吉日参拝いたしました。
7月27日三池藩主立花家よりご参拝
御祭神のご命日にあたる7月27日三池藩主立花家当主様の参拝がございました。夕刻には大正町お祭り広場「祇園六山巡行」をご覧いただき、翌日は三池新町弥剱神社にご参拝されました。
氏子崇敬者の方のご案内で三池の街を散策されました。関係者の方々に感謝申し上げます。
御代替り~平成から令和へ~
皇太子殿下ご即位(践祚)五月一日
天皇陛下のご即位をお祝い申し上げます
ご神木
この椎の木は幹がねじれながらも倒れずに長年当地を見守っています。倒れずにあるのは後ろにハゼノキが支えているからです。正面は椎の木しか見えませんが後方をよくご覧になってください。自然の妙に驚かされます。
ご神木として大切にされています。
厄除け祈願
厄年はさまざまな災難にあいやすいといわれています。
数え年で男性は数え年25歳・42歳・61歳女性は数え年19歳・33歳・37歳を大厄(たいやく)その前後の年を前厄(まえやく)・後厄(あとやく)といい神社にお参りをして災厄をさけるために厄祓い(厄除け・やくよけ祈願)を受けましょう